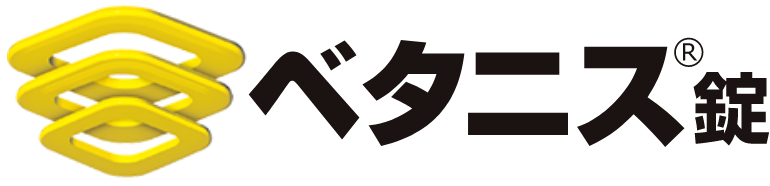西野好則先生が語る患者さんとのコミュニケーションの極意。最終回では夜間頻尿の治療アプローチ、高齢患者さんとのコミュニケーションのコツ、診察室の外での患者さんやご家族を支える取り組みについて紹介します。西野先生の「全人的医療」を実現するためのコミュニケーションの考え方と実践を、ぜひ日常診療でお役立てください。
西野クリニック院長
西野好則先生
<プロフィール>
1990年高知医科大学医学部卒業。95年岐阜大学医学部助手。その時に同大学附属病院で排尿障害専門外来を開設。その後、同大学講師や東海中央病院泌尿器科部長、岐阜市民病院泌尿器科副部長を歴任。2005年に医療法人好誠会西野クリニックを開院。岐阜大学非常勤講師、泌尿器科学会専門医・指導医。ベストドクターズ社の「The Best Doctors in Japan™」(医師間の相互評価)に5期連続で選出された。
非専門医の先生方からは、「夜間頻尿は、その原因の特定や説明、目標設定が難しい」という声が多いですが、夜間頻尿の診療において大切なのは、「夜間頻尿の原因は一つではなく、個人によって異なる」という点を患者さんに理解していただくことです。夜間頻尿には「膀胱蓄尿機能の低下」「多尿・夜間多尿」「睡眠障害」の3つの原因があります。さらにそれぞれの原因をきたす疾患として、過活動膀胱や高血圧、心不全など様々な因子が関わっています(図)。治療法を選択するにあたり、一人一人異なる夜間頻尿の原因を見極める必要があります。
そのため、患者さんの症状を聞きながら、その原因を特定していくのですが、医院での専門的な検査も、ご自宅での排尿日誌もなかなかハードルが高い場合がありますよね。
そんな場合にご紹介したいのが夜間の尿量だけ測定する「夜間だけ排尿日誌」という手法です。
高齢者の膀胱容量は大きい方でも300mL程度とされていますので、夜間の総尿量が600mLであれば夜間多尿の可能性が高いです。1回あたり200mLくらいが排出されていれば、膀胱は正常と判断できます。夜間の総量が300~400mLくらいで、1回の排尿量が100mL程度と少ない場合は膀胱容量の問題が考えられます。
このように、「夜間だけ排尿日誌」でも診断の大きな一助となります。当院では、検尿コップを患者さんにお渡ししていますが尿瓶でもいいと思います。
夜間頻尿は治療しても0回にはならない、理想の改善には至らないことも多いですが、先に述べたように行動療法も含め治療に取り組んでいく中で、患者さんが納得される着地点に辿りつけるよう、とことん伴走することが重要です。
Vol.1でご紹介した患者さんとのコミュニケーション上の工夫に加えて、特に高齢患者さんで意識していることは、その方の長い人生に敬意を払い接することです。診療中の会話の中で昔話を聞き、どんな仕事をしていたのか、リタイア後はどのように過ごし、今どうされているのかといった人生背景を聞き、その上で今は何を悩まれているのかを理解していく、それが高齢者診療の第一歩と考えています。
治療において特に問題となるのは、治療への意欲が低く、諦めの気持ちがある場合です。私はこうした患者さんに対して、年齢に関係なく排尿障害を克服して元気に過ごしている方が多いことをお伝えし、「歳を取ってきたからこそできることや考えることがあるので、喜んで歳を取りましょう。そのために少しでも不調な部分は修繕していきましょう。諦める必要は全然ありませんよ」と話します。トイレが間に合わないからと頻繁にトイレに行き、膀胱を使わないでいると、膀胱は硬く伸びなくなってしまい、どんどん漏れるようになってしまいます。将来的にパッドやおむつが必要になる可能性もあります。
でも、諦めずに膀胱に尿を溜めようと頑張っていると、膀胱はやわらかく伸びるようになって、また尿を溜められるようになる可能性があることを説明し、モチベーションアップを図っています。そして症状の改善が見られた時には、「え、1回減ったの?すごいね!」と一緒に喜びます。これは非常に大事なポイントで、治療意欲の向上に繋がると考えています。
私は診察室内だけでなく、診察室の外でも患者さんと積極的にコミュニケーションを図ることが大切だと考えています。その一環として、これまで新型コロナウイルス感染症の影響で中断していたクリニックの取り組みを再開する予定です。
まず、「排尿障害に関する教室」です。これは、勉強会を兼ねた井戸端会議のような場で、毎回特定のテーマを設定し、患者さんと医療スタッフが一緒に話し合います。患者さん同士の意見交換や情報共有ができるだけでなく、私たち医療スタッフが患者さんの悩みを深く理解する貴重な機会となっています。
次に、看護師が患者さんのご自宅を訪問し、夜間頻尿に関する調査を行う活動です。訪問時には、ご自宅の状況を確認し、部屋の構造やトイレまでの動線、水飲み場や冷蔵庫の位置などを調査します。調査内容は私も共有し、その上で、夜間頻尿の改善に向けた具体的なアドバイスを患者さんやご家族に提供しています。この取り組みを通じて、患者さんの生活環境に寄り添ったサポートが可能となり、満足度向上に繋がると考えています。
さらに、今後新たに企画したいと考えているのが「ウォーキング大会」です。健康に良い歩き方を学ぶクラブ活動のようなものをイメージしており、患者さんと実際に一緒に歩くことで、より深いコミュニケーションを図りたいと考えています。この活動を通じて、患者さんに健康的な生活習慣を提案し、治療意欲をさらに高めることができればと思います。
排尿障害の診療における患者さんとのコミュニケーションの重要性について、4回にわたってお話ししました。排尿障害の診療においては、羞恥心や将来への不安、診察・検査への不安など様々な心理的葛藤を抱えた患者さんが多いため、医師のみならず、看護師、スタッフが連携して繰り返し患者さんに声がけを行うことが重要です。また、患者さんの生活習慣は症状悪化の要因となるため、日常の会話や雑談の中から問題点を汲み取り、適切なアドバイスを行うことが、治療成果の向上に寄与します。
「全人的医療」という言葉がありますが、その基本は患者さんとのコミュニケーションです。医療従事者にとっても、患者さんとのコミュニケーションがスムーズになることで治療効果が上がり、患者さんの笑顔を見ることができるのは大きな喜びであり、達成感に繋がります。当施設での取り組み事例が、排尿障害患者さんの診療に携わられる医療従事者の皆さまの参考になれば幸いです。
ところで、連載の冒頭でお話しした、私が研修医時代にコミュニケーションの重要性に気づくきっかけを与えてくれた患者さんについてですが、その方は亡くなられて30年経過しますが、今でも奥様と息子さんは、時折クリニックを訪れてくださいます。先日は、誕生されたお孫さんを連れていらっしゃいました。このように、長きにわたり地域の方々と親しく交流できることは、私やクリニックのスタッフにとって大切な財産であると感じています。
この連載でご紹介した事例や工夫が、排尿障害を含む幅広い疾患に対応される医療従事者の皆さまにとって少しでも参考になれば幸いです。患者さんとの信頼関係を築き、その人生に寄り添うことで、医療の可能性はさらに広がると確信しています。
図 夜間頻尿の原因
監修:西野好則先生
日本排尿機能学会/ 日本泌尿器科学会, 編. 夜間頻尿診療ガイドライン[第2版](2020)を参考に作成。
関連情報
アステラス製薬株式会社の医療関係者向け情報サイトにアクセスいただき、ありがとうございます。
アステラスメディカルネット会員の方
medパス会員の方
会員登録されていない方
会員向けコンテンツをご利用の方
会員になると以下のコンテンツ、サイト機能をご利用いただけます。