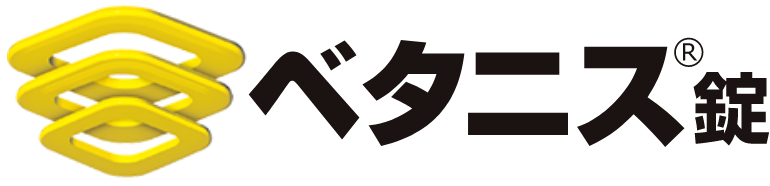センシティブな相談が多い泌尿器科診療において、患者さんとの信頼関係を築くことは、治療を円滑に進める上で欠かせない要素です。西野クリニック院長の西野好則先生は、笑顔を大切に、専門用語を避け、雑談も交えながらの温かい対話を心がけています。こうしたフレンドリーなコミュニケーションは、患者さんの心を開くだけでなく、ご家族との「家族ぐるみ」の信頼関係へと発展することもあるそうです。西野クリニック院長 西野先生へのインタビュー第2弾では、信頼を深めるためのコミュニケーション術に迫ります。
西野クリニック院長
西野好則先生
<プロフィール>
1990年高知医科大学医学部卒業。95年岐阜大学医学部助手。その時に同大学附属病院で排尿障害専門外来を開設。その後、同大学講師や東海中央病院泌尿器科部長、岐阜市民病院泌尿器科副部長を歴任。2005年に医療法人好誠会西野クリニックを開院。岐阜大学非常勤講師、泌尿器科学会専門医・指導医。ベストドクターズ社の「The Best Doctors in Japan™」(医師間の相互評価)に5期連続で選出された。
今回は、患者さんと話す際に気を付けているポイントをいくつか挙げたいと思います。
最も重視しているのは笑顔です。看護師や受付スタッフにも、患者さんと接するときは笑顔を絶やさないように伝えています。ただし、常に笑顔でいることは疲れる場合もあるため、スタッフは一般的な人数よりも多くし、仕事中に自由なタイミングで休憩へ行って水分補給や甘いものを食べてもよいことにしています。
患者さんと話す際には、電子カルテを見ながらではなく、患者さんをしっかり見て話すこと、そして堅苦しくならないように注意しています。私自身、医師であることを忘れ、患者さんを「近所の人」と考え、友達になるような感覚で接することを心がけています。
医療専門用語、例えば「尿意」「排尿」「切迫感」「頻尿」などを用いず、平易な言葉で会話することです。こうした表現を避けても、わかりやすい言葉で症状や重症度を確認することが可能です(表)。
再診時にも配慮すべき点があります。患者さんが診察室に入ってきた際に、「調子はどうですか?」という言い方はしないようにしています。それはその問いかけに対して患者さんは「調子悪い」と答えづらいからです。そのため「変わったことはなかったですか」とか、「何か嫌なことはありませんでしたか」という尋ね方のほうが、会話が進みやすいと思います。
病気のことのみならず、雑談も信頼関係の醸成に役立ちます。
旅行中に尿意で苦労したこと、家のリフォームでトイレを改装したこと、久しぶりに息子さんが帰郷されることなど、どんな話題でも良いのです。
雑談の内容は、不思議と記憶に残っていますが、「大切な雑談」はカルテにメモしておきます。再診時にこれまでの雑談内容に触れながら会話ができるとコミュニケーションはぐっと深まります。例えば長野に旅行に行った話を聞いていた患者さんに対しては、「この前は長野に旅行したって言っていたけど、次の旅行の予定は立てていますか?」というような話をすると、「自分のことを覚えてくれているんだ」と思い、患者さんとの距離がぐっと縮まり、さらに色々と話してくれるようになります。それら日常のエピソードから病状に関する情報を得られることもありますので、患者さんと友達になるような感覚で雑談をすることは、患者さんにとっても医者にとっても充実した外来になるのです。
患者さんとコミュニケーションを取ることのメリットは、よりよい治療が可能になるということです。患者さんとの距離が縮まり、本音を話していただけるほど、私の話すことも信頼して聞いてくれて、治療が円滑に進むようになります。また患者さんの信頼が得られると、ご家族の病気についても相談されたり、そこからご家族が受診されたりすることがあります。受診される家族が増えていくと「家族ぐるみ」の関係となり、そこから様々な情報を得て、治療に活かすことができます(図)。
加えて患者さんと気軽に話をすることで私自身が楽しく仕事ができます。
患者さんとの深いコミュニケーションで患者さんやご家族、地域の健康に貢献でき、自分も楽しい。私にとってコミュニケーションは最良の治療手段の1つです。
今回は、患者さんとのコミュニケーションがいかに診療を豊かにし、治療の質を向上させるかをお話ししました。笑顔で接すること、わかりやすい言葉を使うこと、雑談を通じて患者さんの本音に触れることは、信頼関係の構築のベースとなります。また、患者さんとの距離が縮まることで、ご家族や地域の健康支援にも繋がります。われわれ医療従事者の表情や言葉が、患者さんの心に大きな安心感を与えうることを忘れてはならないと考えています。
表 直接的表現や専門用語の言い換え
提供:西野好則先生
図 コミュニケーションが生む信頼関係のメリット
情報提供・監修:西野好則先生
関連情報
アステラス製薬株式会社の医療関係者向け情報サイトにアクセスいただき、ありがとうございます。
アステラスメディカルネット会員の方
medパス会員の方
会員登録されていない方
会員向けコンテンツをご利用の方
会員になると以下のコンテンツ、サイト機能をご利用いただけます。