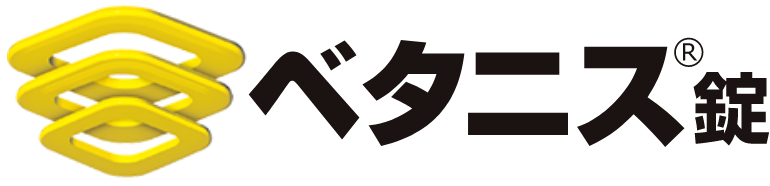泌尿器科を受診する患者さんの多くは、「恥ずかしい」という気持ちを乗り越え、勇気を出して来院しています。その背景には、センシティブな尿の悩みが生活や仕事、人間関係に大きな影響を及ぼしている現実があります。西野クリニック院長の西野好則先生は、「患者さんが話しやすい環境を整えることが何より重要」と語ります。初診時に驚かず共感的に接することで患者さんの不安を軽減し、さらに詳しい情報を引き出す工夫が治療成功の鍵になります。
西野クリニック院長
西野好則先生
<プロフィール>
1990年高知医科大学医学部卒業。95年岐阜大学医学部助手。その時に同大学附属病院で排尿障害専門外来を開設。その後、同大学講師や東海中央病院泌尿器科部長、岐阜市民病院泌尿器科副部長を歴任。2005年に医療法人好誠会西野クリニックを開院。岐阜大学非常勤講師、泌尿器科学会専門医・指導医。ベストドクターズ社の「The Best Doctors in Japan™」(医師間の相互評価)に5期連続で選出された。
患者さんとのコミュニケーションの重要性を強く実感したきっかけは、研修医時代に担当した40代の腎がんの患者さんとの経験です。当時、私は上司の先生の補佐役で、治療に関する説明は上司が行い、私はその場で話を共に聞いている立場でした。
しかし、患者さんの通院や入院が長引くにつれ、研修医の私ができることとして、その方のお仕事や日常生活、さらには親子のコミュニケーションの悩みなど、ご家族との関係についてもお話を伺うようにしました。やがて患者さんの奥様や中学生の息子さんとも話すようになり、それぞれの立場での悩みや思いに触れる機会が増えていったのです。ときには、気持ちが少しでも明るくなるよう、私なりの意見をお伝えすることもありました。
その患者さんが亡くなられた際、奥様や息子さんから「病気のことで一緒に泣き、親身になって話をしてくれてありがとう。先生のおかげで救われました」と感謝の言葉をいただいたのです。そのようなことを言われるとは思ってもおらず、ただ一生懸命にお話をしていただけでしたが、医師は治療について話すだけでなく、患者さんやご家族と会話を交わすことも大変重要であると、医者になって最初に学んだのです。それ以来、患者さんが生きてきた人生を色々な角度からお聞きしていくことが習慣となっていきました。
命に関わらない疾患であっても、患者さんやご家族の話に耳を傾けることの大切さは変わりません。当院の外来患者の約7割は頻尿などの排尿障害に悩む方々ですが、センシティブな悩みですし、その要因は多岐にわたり、困っている内容や程度も個々に異なります。また、夜間に頻繁にトイレに行く音がしたり、介助が必要になったりすることにより、本人のみならずご家族まで困っておられるケースもあります。
疾患の全体像を把握し、予測される要因に対応して治療の目標を考え、ご本人とご家族の満足度を向上させるためには、コミュニケーションを通じて様々な情報を得ることがとても大切であると考えています。
患者さんと深いコミュニケーションを取るためには、患者さんの悩みに共感し、その上で心を開ける環境づくりが重要です。特に初診時の対応が鍵となります。患者さんの中には、「恥ずかしい」という気持ちを乗り越えて勇気を出して受診された方も少なくありません。そうした患者さんに安心してもらうためには、恥ずかしさを感じさせない会話の工夫が必要です(図)。
以前、泌尿器科を受診することに恥ずかしさを感じる理由を患者さんに尋ねたところ、「医師の表情が気になる」「看護師に『この人、尿失禁があるのね』と思われたら嫌だ」という声が多くありました。
このような患者さんの不安を軽減するためには、まず話に驚かないことが大切です。たとえば患者さんが「実は尿漏れがひどいんです」と話した際、驚いたような反応を示すと、患者さんは話しづらくなります。その代わりに、「そうですか、それはよくあることですよ」と安心させる言葉をかけ、さらに「そういうことはどんどん言って貰えるといいです。他にも何か気になることはありますか?」「下着、替えたりされているのですか?」「パッドは1日何枚使用されているのですか?」などと具体的に深掘りして尋ねると、患者さんは色々と話しやすくなりますし、こちらはその中から症状の重症度を探るなど、より詳しい情報を得ることができます。
患者さんが恥ずかしいと感じる可能性がある表現は、できる限り避けるよう心がけています。たとえば、「尿漏れ」という言葉を使わず、「間に合わないことがありますか?」や「下着が汚れることはありますか?」といった表現に置き換えています。また、患者さんの中には「恥ずかしい検査」や「痛い検査」を想像して不安を抱く方もいます。そのような検査はほとんどの場合必要ないことを事前に説明することで安心していただけることがあります。
泌尿器科の受診を恥ずかしく思う気持ちは、男性よりも女性で大きい印象があります。ただ、だからと言って女性患者さんが男性医師よりも女性医師のほうが話しやすいと思っているかというと、そうでもないなと感じています。男性医師でも恥ずかしいという気持ちに配慮してうまく会話を進められれば、女性患者の信頼を得ることは可能だと思っています。逆に女性医師であっても配慮がないと患者さんの気持ちは離れていくと思います。
患者さんが「恥ずかしい」という気持ちを乗り越えてでも受診される背景には、多くの場合、大きな生活上の困難や不安があります。その気持ちに共感することは、深い会話をする上で欠かせません。こうした背景を理解するために、「なぜ病院に行こうと決断されたのですか?」と尋ねます。この質問への答えが、患者さんの最も困っている症状や状況を示すことが多く、それが治療のゴールや満足度向上に繋がるからです。
具体例としては、排尿障害により生活リズムが乱れる、仕事に支障をきたす、夜トイレに起きて睡眠不足で困るなどです。女性の場合は人の目が気になっていることが多く、グループ活動で自分だけトイレに行くのが気まずい、スポーツをしたいけれど、漏れが気になって楽しめない、といった声を聞きます。また、「今この状態だと5年後、10年後にはどうなってしまうのか?」と将来の不安を抱えて受診される患者さんもいます。
人の目を気にされている患者さんには「同じような症状の方は他にもたくさんいますよ」、将来の症状が不安な方には「それほど深刻に捉えなくて大丈夫ですよ」といった言葉をかけるなど、不安を軽減するような言葉を選んでお話しするようにしています。
中には、「週に1回、少量の尿漏れ」など、医師の目から見ると軽症に思える症状の方もいらっしゃいますが、患者さんにとっては重大な問題で、日常生活に与える影響は大きく、精神的苦痛を感じているかもしれません。悩みの重さは人それぞれですので、どんな受診理由でも、それが非常に大きな心的負担となっていると認識して、患者さんと向き合っています。
今回は、泌尿器科診療において患者さんと信頼関係を築き、診療を進めていくための初診時のポイントについてお話ししました。患者さんが抱える悩みを的確に理解するには、共感を示しつつ、恥ずかしさや不安を和らげるコミュニケーションが重要です。また、受診を決断された理由を尋ねることも、患者さんの一番の困りごとを引き出す方法として有効です。患者さんの心の負担を軽減し、身体だけでなく生活全体をサポートする視点での診療を心がけることが、信頼と満足度向上の鍵となります。
図 恥ずかしさを感じさせないコミュニケーション
情報提供・監修:西野好則先生
関連情報
アステラス製薬株式会社の医療関係者向け情報サイトにアクセスいただき、ありがとうございます。
アステラスメディカルネット会員の方
medパス会員の方
会員登録されていない方
会員向けコンテンツをご利用の方
会員になると以下のコンテンツ、サイト機能をご利用いただけます。